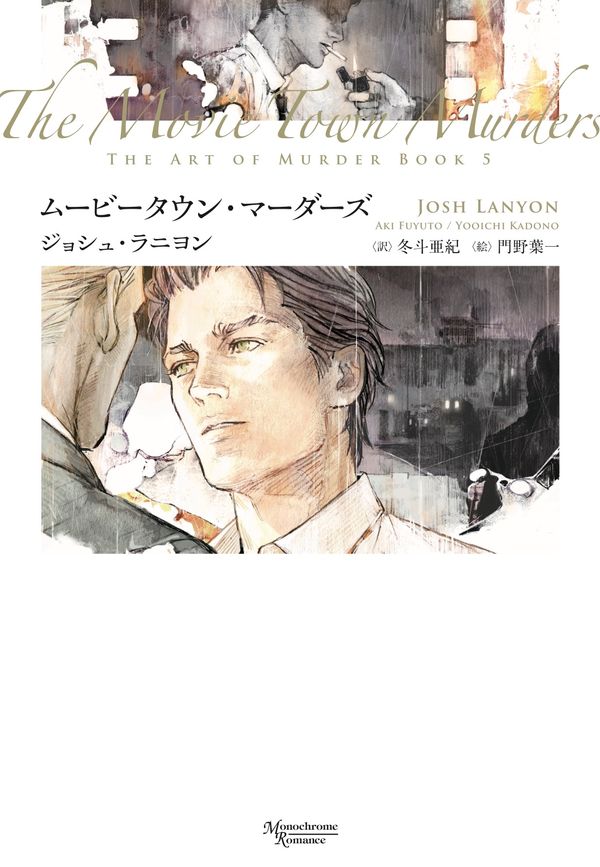
ムービータウン・マーダーズ
(殺しのアート5)ジョシュ・ラニヨン
■1
キャプスーカヴィッチとの面談の途中でジェイソンは悟った――クビになることはないと。
FBIの美術犯罪班【ACT】所属のジェイソン・ウエスト特別捜査官は心底啞然とし、おかげで、ACTを管轄する窃盗課主任の言葉をいくつか聞きとばした。
「何とも皮肉な話だと思わないか?」とキャプスーカヴィッチに聞かれる。
ジェイソンは「はい」と絞り出した。
ああ、じつに苦い皮肉だ。サムもそう思うだろうか?
「言っておくが、私は“一度のミスは甘く見るべき”という考えには与【くみ】しない」
ジェイソンは半ば飲みこむようにかすれた声で「はい」と答えた。
「あなたがやり直すチャンスを与えられるのは、ウエスト、このただ一度の例外を除けば、六年間の働きぶりが模範的なものだったからだ。一度の過ちを許される権利を、それによって与えられた。一度。一度きりだぞ。次はない。ほかの部下なら誰だろうと、バッジと銃を取り上げて追い出している」
「理解しています」鋭い息を吸いこんだ。「くり返しになりますが、大変申し訳――」
「聞きたくない」
キャプスーカヴィッチのいつもは温かな青い目が、今は氷点下だった。
「総論としては、今回の件には酌量に足る余地があった、ということだ。私も同意見だ。この判断が間違っていたと思わせないでくれ。このチャンスを台無し にしてくれるな」
七分後、ジェイソンは専用エレベーターを降り、防犯カメラの前を通り、受付カウンター、警備エリア、巨大な二本の旗(一本は昔ながらのアメリカ国旗、もう一本はFBIの局旗)の間の巨大な青と金のFBIの紋章の上を、そしてセキュリティゲートの金属探知機を通過した。防弾ガラスのドアを押し開け、エアコンが効いた局の静かな建物から、暑くてやかましい七月の昼下がりのペンシルバニア大通りに出ていた。
現実の世界に戻ってきたと――しかも職を失わずにすんだと、そのことに頭がくらくらする。夏の空気は、排気ガスと熱されたコンクリートの匂いがした。首が薄皮一枚でつながったピンチの匂いも。
IDカードのストラップをポケットにしまうと、白茶色のコンクリートの外壁沿いに歩いた。黒枠にはまった不透明なブロンズ色の角窓が規則正しく並んでいる。J・エドガー・フーヴァービルというあだ名に似て、無骨な建物だ。事実、この建築スタイルはブルータリズムと呼ばれている。非情【ブルータル】とは、何とも鼻につくとり合わせ。
ジェイソンは見つけたタクシーにすぐ乗りこんだ。
「クリスタル・シティのダブルツリーまで」
タクシーは停まったか停まらないかのうちに走り出し、匿名の人々の車列にするりと溶けこんだ。上流を目指す魚の一匹。
ジェイソンはシートに体を預け、汗のにじむ額を袖で拭ってネクタイをゆるめてから、携帯電話を取り出した。サムの番号を押す。
二コール目にサムが出た。
『今どこだ』
「空港に向かってます。というか、そばのホテルに。でも大丈夫だった。俺は。まだ雇われてる。首がつながった」
一時間前のジェイソンは、どれだけ甘くても無給の停職処分か、ストレス休暇に追いこまれるだろうと見ていた。どちらでも運がいいと思っていたくらいだ。だが現実【・・】はあまりにもうまくいきすぎて、まだ実感すら湧いてこない。
サムが簡潔に言った。
『スカイドームラウンジで会おう』
「会おうって……まだDCにいるんですか?」
『そうだ』
ロサンゼルスからワシントンDCまで同じ便で飛んできたとはいえ、サムはすぐクワンティコへ車で向かい、スタッフォードの自宅へ戻ることになっていたはずだった。
ジェイソンは、耳から離した携帯電話を疑り深く眺めた。また耳に当てると憂鬱に言い返す。
「俺はもう運の尽きだと思ってたってことですか」
『いや。キャプスーカヴィッチほど賢ければ、まとめてゴミ箱行きのような雑な真似はしないと思っていた。だが予想が当たるとは限らない』
「俺は、クビになると思ってました」
本心だった。ジェイソンは上司との面談に、銃殺刑に臨むくらいの希望しか持たずに向かったのだ。
抑えた声からでさえ、サムの『お前は長年行方不明だったフェルメールを見つけた捜査官だ、ウエスト』という言葉の辛辣さははっきり聞こえた。
『お前を解雇するのは、マスコミ受けが悪い』
痛い一言。
だがそれもたしかに、キャプスーカヴィッチが言及した“総論”とやらの一部なのだ。LA支局のロバート・ウィート部長はジェイソンをクビにしたがるどころか、逆に、ソルトレイクシティ支局の美術犯罪班がジェイソンの“秘密作戦”の手柄を「横奪りしようとしている」と騒いだ――もっと攻撃的な言葉で。さすがにジェイソンの行動を自分が認可【・・】したとまでは言わなかったが、ウィートはそれに近いことは言った。出世欲の強い人物で、ここ十年で最大級の絵画再発見の栄誉を、LA支局の――そして自分の――ものにしようと躍起なのだ。
「まあ、そうですね」
『着いたら話そう』
サムが通話を切った。
ジェイソンはシートに沈みこみ、また額を拭った。
スカイドームラウンジは、アーリントンのクリスタル・シティにあるヒルトン北棟の回転レストランだ。地味な宇宙船のような内装は退屈だが、客を呼ぶのはベージュ色のインテリアでも、メニューのトマホークステーキでさえない。ガラス張りのドームは四十五分もかけずにぐるっと一回転し、天気がよければ(今日のように)国防総省【ペンタゴン】やDC、ポトマック川の眺望はじつに見事なものだった。
その上、スカイドームのバーテンダーたちは、瓶からグラスに直注ぎする美学を知っている。
ほとんど客のいないラウンジを見回したジェイソンは、ガラス壁そばの席にサムを見つけた。ダークスーツの上着を椅子の背にかけ、ノートパソコンで仕事をしている。しばし、ジェイソンはいかにもサムらしい姿を目で楽しんだ。美形、というタイプではない横顔は読んでいるものに集中し、まくり上げられた白いシャツの袖口から日焼けした筋肉質な腕がのぞき、上等な靴先の片方が無意識にせわしないリズムを刻んでいる。
近くのテーブルでは、二人のお洒落で魅力的な女性がクスクスと囁き交わしながら、サムを値踏みしていた。
それ以外、レストラン内は閑散としていた。中央にはぽつんとDJブースが鎮座し、それを囲む寄せ木張りの小さなダンスフロアは三組もカップルが入ればいっぱいだ。天井からは大画面テレビが四台吊り下げられ、ニュース専門局が流されて、誰が協力的でないのまとまらないのと、いつものよくあるニュースを報じている。
ジェイソンが近づくと、サムが顔を上げた。いかめしい表情がやわらいだが、見方を熟知していないと認識できないほどのものだ。サムが金縁の眼鏡を外し、ノートパソコンを閉じた。
「どうも」とジェイソンは言った。サムがホテルで待っていたなんて、まだ現実味がない――もちろんうれしいが。
「ああ」サムがジェイソンを観察した。「大丈夫か」
ジェイソンはうなずき、向かいの椅子を引いて座る。
「ええ。ただ……驚いています」
すべてに対して。じつのところ緊張の余韻でまだくらくらする。間一髪だった時のように。
最悪の結果に備えて心がまえはしていた。その最悪が訪れなかった事実を、まだ受け止めきれないでいる。
サムがうなずきで合図すると、バーテンダーが小さなダンスフロアをこちらへ横切ってきた。
「何を飲む?」とサムが聞く。
「生ビールをどれか」とジェイソンはバーテンダーに伝えた。
彼女はうなずく。サムの肘横にある空のロックグラスへ目をやった。
「おかわりお持ちしますか?」
サムは首肯した。バーテンダーが去っていくと、ジェイソンに聞いた。
「それでどうなった」
ジェイソンはうかがうように問い返す。
「キャプスーカヴィッチがあなたと電話したと言ってましたけど?」
「金曜に話はした。彼女はまだ決めかねていた」
ジェイソンはいびつな笑みを向けた。
「なら、この皮肉を楽しめるのでは。キャプスーカヴィッチによれば、俺の祖父もロイ・トンプソンも双方他界している以上、今回の件はそもそも“関心を寄せるべき”ものではないと――なかったんだそうです」
サムは眉を寄せて聞いている。
「トンプソンがまだ存命で、裁判にでもなれば、祖父から美術品の横奪を命じられたという彼の主張が俺の立場を微妙なものにしたかもしれません――そうなれば、俺の捜査対象に祖父が深く関わっていたという、ここが肝心ですが、主張【・・】がなされたでしょうし」
サムが腑に落ちた瞬間が、ジェイソンにはわかった。サムの目――FBIの紋章と同じ何もよせつけぬ青――がかすかに光る。口元が苦笑に歪んだ。
「お前の捜査対象は、美術品の所有者が誰なのかであって、トンプソンが窃盗を行ったかどうかは関係ない」
「そう。そうなんです」ジェイソンは長い息をついた。「祖父がトンプソンに、美術品やその他の品を持ち出すよう――絶対にありえませんが、命じたか、トンプソンが自分の意志で美術品を“解放した”のか、どちらだろうとそもそもあの宝が盗品だという事実は変わらない」
サムは考えこんでいた。
「美術品を入手した経緯は捜査結果に影響しない、か」
ジェイソンは笑い、目を拭った。この話はまだつらい。
「つまるところ、そうです。俺も頭に泥でもつまってたんでしょうね、あれはどうかしてた。キャプスーカヴィッチが問題にしてるのは、倫理違反じゃない。問題なのは、俺が【・・】倫理に違反すると考えていたこと――それでも行動に出たことだ」
「“犯罪よりも隠蔽のほうが高くつく”」サムが引用して、すぐにつけ足した。「お前が犯罪をしたわけじゃないし、するとも思わんが」
今、そう思ってくれているのがありがたい。三日前のサムはそうは考えていなかったように見えた。
「ええ。俺はただ……過剰反応してしまった。どうしてかわかりません」
「俺にはわかる」サムはそう切り捨てる。「お前にもわかっているだろう。キャプスーカヴィッチもだ」
ジェイソンが精神的に疲弊して神経過敏だという見解を、サムはこれまで遠慮なく示してきた。おそらくキャプスーカヴィッチにも話しただろう。ジェイソンとしては愉快ではないが、直近の出来事を見ると反論もできない。
サムは自分の態度や反応に思い至ったのだろう、補足した。
「だからこそ、事の前に【・・】倫理委員会に話しておくのが肝心なんだ」
「そうですね。たしかに」
サムはジェイソンの行動を、ジェイソン自身にも劣らず否定的に見ていたのだった。笑い話になることはないだろうが、二人にとっていい教訓になった出来事ではあった。様々に。
ジェイソンは暗いまなざしを投げた。
「そう言えば、金曜にあなたがキャプスーカヴィッチに電話したのは、モンタナを発つ前ですよね?」
サムの淡い眉が問い返すように上がる。
「LAに着く前。俺と話をする前」
二人の関係は完全に終わったと、ジェイソンが信じ切っていた時間。そしてまた、サムのほうもあの時は、彼らはもう終わりだと信じていたはずだ。自分で終わりにしたのだから。
それはジェイソンの勝手な見方かもしれないが。何しろあの時も今も、サムは無言のままだ。
そして沈黙を続けている。
「ありがとうございます」ジェイソンは声を整えた。「本心からです。電話する義理はなかったのに。あなたの……色々なことへの、気持ちを思うと、特に」
「俺は自分の意見をキャプスーカヴィッチに伝えた。だが、ほかの班の長に方針を押し付けることはできない。できたとしても、俺はしない」
「わかってます」
それでも、キャプスーカヴィッチによれば、サムはたしかに――彼なりのやり方で――ジェイソンのために取りなそうとしたのだという。それだけでジェイソンにとっては驚愕だった。まるで、太陽がその気になれば西から上って東に沈むこともあると知らされたように。
ボズウィン地方支部内のサムの臨時オフィスで対立した後、二人は随分と長い旅をし、変化を遂げた。モンタナとカリフォルニアを隔てる千五百キロの距離とは関係のない、長い旅だ。むしろその旅の多くは、キャロル・カナルに面したジェイソンの小さなバンガローの中で進んだ。
「個人的感情を置いても、お前は優秀な捜査官だ、ウエスト。ACTの輝かしい注目株。お前を解雇するのは大いなる損失となるだろう。様々にな」
ジェイソンは反論の口を開いたが、サムが重ねた。
「それに俺の個人的な感情を言うなら」と奇妙な笑みを見せる。「わかっていると思うが、俺はお前のためなら、大抵のことはやる」
ビール片手に泣くような真似はしたくない――そもそもビールがまだ来ていない。ジェイソンは淡々と言った。
「ジョージも電話してくれたんですよ、恩赦をたのみにね」
冗談めかそうとはしたが、あの穏和な管理官ジョージ・ポッツが彼を救おうと動いてくれたのは、ジェイソンにとってサムの行動と並ぶくらいに大きなことだった。
バーテンダーが飲み物を運んでくる。サムは勘定をまとめて伝票につけてもらっているようだ。クワンティコへ出立する気はない、ということだろうか?
ジェイソンはビールの入ったフロストマグを手にした。サムが自分のグラスの底をジェイソンのグラスと軽く合わせた。
「おかえり、ウエスト」
返事がわりにジェイソンはうなずく――この頃はおかしな出来事にやたら胸がつまる。「ジェロニモ」と乾杯の声を返して、長々とビールをあおった。
「何にせよ、さっきも言ったが、お前は得難い人材だ」
サムがグラスに口をつける。だがジェイソンと合わせたまなざしには、不思議な形で心に伝わってくるものがあった。共感とは言えないものの、そこには深く完全な理解がある――それが腹の底をおかしなふうにざわつかせ、温かな脱力感をもたらす。
もしかしたら、いや疑問の余地なくフェアでも正確でもない思いこみだが、ジェイソンははじめから、サムの……愛情は、条件付きだと感じていた。だが今の二人はその先の、互いを認め許し合う、道なき地へたどりついた気がする。未来に何が待つかはわからないが、今のジェイソンはかつてないほど、サムからの思いを確かなものとして信じられるようになっていた。
ジェイソンはビールを飲み、ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港へ到着する旅客機を眺めた。数時間のうちに自分もそこから飛び立つのだ。だが今は、この瞬間の先は考えまい。隙間で手に入った、サムとの短い時間。いつまた一緒の時と場所で出くわせるかは神のみぞ知ることだ。
不意に、キャプスーカヴィッチのオフィスでの面談を思い出し、含み笑いがこぼれた。
「どうした」とサムが聞いた。
「思い出したことが。キャプスーカヴィッチが言ってましたが、J・Jが彼女に電話をかけてきて、現場訓練期間中に三人もパートナーを変えるのは嫌だから、俺をLA支局に残してほしいと言ってきたそうです」
サムがウイスキーサワーでむせた。「本気か」と手早く顎を拭う。
ジェイソンは笑った。
二人はさらに数杯飲み、さしたる話はしなかった。ジェイソンの脳はキャプスーカヴィッチとの面談をくり返し流し、耐えがたい一瞬ずつを再生してくる。まだ自分にキャリアがあるというさもしい安堵感と、それを失う寸前まで行ったという情けなさの間で心がぐらつく。
五時を回る頃にはバーは満員になり、騒がしさも増していた。
サムが眉を上げる。
「夕飯を注文するか、それとも……?」
ジェイソンの心が浮き立った。これで、一つの問いは解けた。サムは泊まるつもりだ。微笑み返した。
「それとも、のほうで。絶対にそっちで」
サムの口元がくいと上がる。椅子を後ろへ押しやった。
■2
エレベーターは混雑していた。
ワシントンDCなので、ホテルには政府機関の職員があふれている。サムとジェイソンは無言で立ち、肩をふれ合わせ、時おりひそかに互いの手をかすめさせながら、のろのろと下へ向かった。一階、また一階と、二人が辛抱強く待つ間、エレベーターは揺れて停まってはドアが開き、人々が流れこみ、流れ出し、またドアが閉まる。
エレベーターの停止音が鳴るたびジェイソンは、知っている相手に――特にありそうなことだがサムの知り合いに――出くわさないよう祈った。
二人が規則に抵触しているからではない。FBIには、局員同士の交際を禁じる規定はない。そうではなく、知り合いに会えばそれだけ足止めになるからだ。
七度、スローモーションの停止を経て、やっとジェイソンの部屋の階に着く。
ついに二人は廊下に出た。鉄の壁掛け燭台と、深紅とオリーブゴールド色のアールデコ調カーペット。あたりは掃除用薬剤の匂いと、あえて控えめに散らされたシトラス系の香りがした。ほのかな照明で緑がかった影がすべてについている。サムとジェイソンにも。二人は少し意識した微笑をさっとかわした。
エレベーターの扉が背後で閉まり、そして一分もしないうちに、ついに二人きりだ。
ジェイソンの部屋からは、明かりがきらめきはじめたワシントンDCのパノラマビューがまだ見渡せる。ワシントン記念塔、ジェファーソン記念館、リンカーン記念堂、そして無論ホワイトハウスの象徴的なシルエットが夕日に映えている。
部屋にはありがちなワークデスク、薄型テレビ、そして何より肝心の、快適なキングサイズのベッドがあった。
ベッドこそ、今、唯一の目的地。
ジェイソンはキーカードをデスクに投げ、ホルスターも外して脇へ置いた。サムがドアをロックし、ブリーフケースとジャケットを角の椅子へ投げる。ネクタイをゆるめながらベッドへ向かうと、そのネクタイをブリーフケースとジャケットの山の上へ放り捨てた。拳銃はサイドテーブルへ置く。
その頃にはジェイソンもシャツとズボンを脱いでいた。微笑みながらサムへ腕をのばすと、慣れた手早さでシャツのボタンを次々外す。サムがジェイソンの首筋に頬ずりしながら、自分のズボンのボタンへ手をのばした。ジェイソンはサムの糊の利いた白シャツを肩から落とし、顎の猛々しいラインにキスをした。
「何の文句もありませんけど、でも、どうして泊まることにしたんです?」
サムが落ちたズボンから足を抜き、両腕をジェイソンの腰に回して引き寄せる。
「WWWDだからだ」
サムの笑みは小馬鹿にするようだったが、むしろ自嘲の笑いに見えた。
「ワールド・ワイド・レスリング・デー?」
「“ウエストならこうする【What Would West Do】”」
「俺なら……」
ジェイソンは笑った。たしかに。もしサムに支えが必要だと思えば、自分ならすべてを投げ打ってでもそばにいる。もっともサムが、そんな深刻な形で彼の支えを必要とするなんて想像できないが。それにサムからはもともと、そう、自分に多くを期待するなと言い渡されていた。まあそれについては幾度となくサムの勘違いが証明されてきたが。この間のモンタナでさえ、あんなに怒ってこちらを見放していたサムが――二人の仲も終わったようだったのに――ジェイソンのために取りなそうとしてくれたのだ。ジェイソンにとってはそれがすべてだった。
「あなたはいい人だ、ケネディ」とジェイソンは重々しく述べた。
サムの口元がピクッと、半分だけの笑みに上がる。
「わかっている」
「俺は他人の評判なんか気にしてませんよ」
サムが笑った。「そうか、俺もだ」とまぎれもない真実で返す。
とにかくジェイソンは、やがて来る別離を先延ばしにできるなら何だろうとかまわない。ただ、今回の別れはモンタナでの別れのように胸がつぶれるものではなく、そのことがうれしい。
二人はベッドにゆったりと横たわり、抱き合って、互いの目をのぞきこんだ。エレベーターではこの瞬間にたどりつけないのではとすら思ったが、今こうしてまた互いの腕の中に戻ると、あらゆる一瞬を味わい尽くしたくなる。
サムにも急ぐ様子はなく、そっとキスを交わし、優しく頬ずりし、やわらかに、そして愛おしそうなキスをくり返した。
平日の昼下がりに手に入った逢瀬。交わしたキスの思わぬ甘さ。
厳密に言えばもう夕方だが。大きな窓の向こうに、夕日でローズゴールドに光る雲が見える。
ジェイソンはうっとりと呟いた。
「キャプスーカヴィッチに新しい任務までもらえましたよ」
「そうなのか?」サムが頭を上げ、息がジェイソンの顔に温かくくぐもった。「どんな」
「カリフォルニア大学ロサンゼルス校【UCLA】への潜入捜査です」
サムの片眉が上がる。
「潜入捜査。それは楽しいだろうな」
その皮肉には同意だが、現状のジェイソンはシベリアの張り込み任務でも喜んでとびついただろう。
「FBIが、カリフォルニアの元上院議員フランシス・オーノのために一肌脱ごうと」
「フランシス・オーノ? また古い名前だな」
「そうなんですよ。かつての、原子力推進派ですね。昔ながらの保守ってやつかと。だからこそ彼がクラークの再選を支持したことが大きくものを言った」
クラーク・ヴィンセントは野心的な共和党下院議員で、ジェイソンの姉であるソフィーの夫だ。じつのところ、DCにいるのにジェイソンが姉の家でなくわざわざホテルに泊まったと知れば、彼女は傷つくだろう。ジェイソンは姉を愛してはいるがクラークを忌み嫌っているので、全力を尽くして必要以上の接触を避けていた。
「ならオーノと面識があるのか?」
「俺? いいえ。会ったことはないですね。彼の孫娘が映画学の教授だったんです。彼女は六ヵ月前に亡くなって、LA市警はそれを“自殺の可能性がある事故”と結論付けた。遺族はありえないと主張している」
サムは憂鬱に言った。
「遺族とはそういうものだ。死因は?」
「自己性愛的窒息」
「それはなかなかだな」
まさに。自分をあえて窒息させて性的快感を高めている最中の死は、品のいい去り方とは言えない。
「事故の可能性はありますが、議員は孫娘が殺されたと信じこんでいるんです」
「映画学の教授を、誰が何のために殺す?」
「それを調べることになるんでしょうね。まだ捜査ファイルを見てませんが」
サムは少し考えをめぐらせていた。
「UCLA。お前の母校だったな?」
「ええ、まあ」
「その上、お前の姉のシャーロットがお前に紹介しようともくろんでいた可愛い美術教師がいるところだな」
サムの口調はそっけない。
「俺は美術教師に興味はないですよ。可愛いのもそうでないのも」
本音だ。サムがアレクサンダー・ダッシュのことを覚えていただけでも、ジェイソンには驚きだった。二月の、ジェイソンの誕生パーティーでちらっと会っただけなのに。
サムの口角が上がった。
「ならいい。浮かれて脇見はするなよ、ウエスト」
ジェイソンは笑いまじりに「脇じゃなくて正面なら見ていいと、ケネディ?」と言い返す。
サムが笑い、たくましい腕でジェイソンの腰をすくってひっくり返したので、二人の目と目、鼻と鼻、口と口が向き合った。
「ハロー」とジェイソン。
サムの口元がピクついた。「やあ」
「今日、残ってくれてありがとうございます。本当に」
「感謝の必要はない」
サムが頭を上げ、その唇がジェイソンの口にかぶさって、計算された巧みなキスをする。ジェイソンは微笑むと、口を開けて舌の侵入を許した。サムがくり返したキスは、今度はもっと勢いにまかせて熱を帯びたものだった。
ジェイソンは、キスで息を吹き返した眠れる美女のごとく喘ぎ、キスを返した。キャプスーカヴィッチのオフィスを出た時から拭えずにいた非現実感や奇妙な乖離感が、すべて消える。サムの手が髪の間をまさぐり、ジェイソンをとらえてキスを深めた。髪の先への愛撫を、足先までに感じる。感電したかのように。
「愛してる」
ジェイソンは囁いた。サムがその言葉を飲みこみ、内に取りこむのを感じる。
小さな奇跡――本来ならサムはもうずっと離れたところに去っているはずで、手は届かないはずなのに、かわりに今ここにいて、心得た指がジェイソンの肌をすべり、そのぬくもりが腰や胸元の薄い肌に温かく、火をともすほどに熱い。肌がティッシュペーパーのように燃え上がらないのが不思議なほどに。サムの指先が乳首をかすめ、敏感な先端を爪ではじく。
ジェイソンは喉から上がる快感の呻きをこらえて唇を嚙んだ――政府関係者がこのダブルツリーホテルにあふれているのを頭の隅で思い出して――が、その気遣いも、ボクサーショーツをつかんで引き下ろしたサムの手がペニスをぐっと握りこむと、散り散りになった。
高い声を上げ、ジェイソンは腰をそらした。サムが体勢を変えたのをマットレスの沈みこみでぼんやり意識する。サムは頭を下げ、ジェイソンのペニスの先端を熱く気持ちのいい口に含んだ。
「ああ、サム、それ……すごい、とてもいい――」
いいどころではない。ゆっくり、強く、熱く濡れた口に吸い上げられる。深く、もっと深く……ペニスがサムの喉奥でヒクついて――このサム・ケネディが【サムから傍点】そんな狂おしいほどに濃密な行為をしているという、それもジェイソンのためにしているという事実が、さらに激しく彼を駆り立てる。
サムはたっぷり時間をかけた。
「もう、イく」
ジェイソンは予告はしたが、隣室も――きっと頭上を飛ぶ飛行機の乗客にも――すでにわかりきっていたことだったろう。
サムは返事がわりに、半分までくわえこんだ。
視界が白熱し、ジェイソンは踵をベッドにめりこませると、荒々しい、揺れ動くようなオーガズムの乱流に身悶えした。血のように熱い体液がほとばしり、サムがそれを飲み下す。それを感じてあやうくもう一度達しかかった。行為の生々しさだけでなく、すべてを受け止めるその信頼――苦しみや誤解に満ちた先週の後では、それがあまりに愛おしかった。
まだどれほど睡眠を欲しているかは、おかしなくらいだ。
とはいえ、セックス直後のこのまどろみは、長々と寝過ごしたこの週末に比べれば軽いものだった。サムが隣室で仕事をしているとか、庭で水をまいているとか、キッチンで夕食の支度をしているとわかっていても、ジェイソンは重い無気力感でなかなか起き上がれずにいたのだった。
常に眠りに飢えていて、重い毛布のように眠気がまとわりついていた。
たしかに、神経衰弱というサムの見立ても、そう外れていなかったのかもしれない。
そうなら回復まで見守っていてくれたサムに感謝だ。
とにかく、目を覚ますと、隅のランプが灯されてシェードが傾けられ、隣にはサムがおり、捜査資料を読んでいた。
ジェイソンが身じろぐと、サムはちらりと目を上げ、薄く微笑した。
「よく眠れたか」
「相手が退屈だからじゃないですよ。誓って」
「わかっている」
サムは眼鏡を外して、ファイルを床に置いた。
体を寄せたジェイソンを腕の中に引き寄せてくつろぐ。サムの胸元を枕にすると、ジェイソンは強く、規則的な鼓動に聞き入った。
少しして、口を開く。
「キャプスーカヴィッチに、一週間の休暇を願い出ました」
サムの驚きを感じとる。もっとも口に出しては「そうなのか?」と返しただけだった。
「どうせ休暇を溜めすぎているので、了承されました」
「仕事から少し離れるのはいいことだ」とサムがゆっくり言う。
「ハンス・デ・ハーンの恋人、アンナに会いに行こうかと」
一拍置いて、サムが答えた。
「それは休暇ではないな。仕事の延長だ」
口調こそさりげなかったが、あまり賛成ではないのがジェイソンにはわかる。ある意味、予想どおりだ。
「そのためだけじゃないですよ。オランダを見てみたいんです。特にフェルメールの出身地をね。でも、ハーンにそれだけの借りがある気持ちもある」
加えて、口に出して認めはしないが、少し国外に出てドクター・ジェレミー・カイザーの手の届かないところに行けるのもたしかに魅力的だった。
「デ・ハーンの行動は彼の判断だった」
「そうですね、借り【・・】は言い過ぎかも。俺はただ、誰かが彼女にデ・ハーンの様子を伝えるべきだと思ってるだけです。デ・ハーンが何を思っていたのか」
サムは静かに、陰鬱に言った。
「俺から言えるのは、そういう行動にはまず、期待どおりの反応は得られないということだ」
頭を上げ、ジェイソンはサムの顔を見つめる。
「何も期待はしてません。ただ恋人に、ハンスは本気で、約束を守って彼女と結婚して子供を持つつもりだったと伝えたいだけで」
「彼女がそれを知らないと思うのか?」
「知っているかもしれませんね。長くつき合っていたそうだから。でも、もしあなたの身に何かあったら俺も知りたい、あなたが俺のことを話していたとか、俺のことを考えていたとか」
サムがぶっきらぼうに言った。
「お前のことを考えるに決まっているだろう」
ジェイソンは短い笑い声を立てた。
「わかりましたよ。うん、ありがとう。覚えておきます。俺も同じだし。でも人によっては、それじゃ足りないかもしれない。ハンスもきっと何かしてほしいと思うだろうし」
サムは溜息をついた。
「お前はとんだロマンチストだな、ウエスト」
ジェイソンは片方の肩を軽くすくめ、指先で軽くサムの、たくましくゆるみのない胸元をなぞり、優しく下へ向かい――サムの下腹がふっと締まるとひそかに微笑んで――まばらでやわらかな毛の向こうから、なめらかなペニスの感触が手を押し返す。
サムが低くうなって、ジェイソンの上にかぶさり、互いの勃起を体の間にとらえた。
ジェイソンの息が速まり、上から突きこむサムに腰を上げて合わせる。突き、押し合い、滑り、それからリズムを見つけて互いと見つめ合う。まなざしを絡めたまま、服だけでなく、あらゆるものを脱ぎ捨てて。ジェイソンは膝を立て、サムがその気なら応じるつもりだったが、サムは彼を抱き寄せて足を絡め、互いに勢いを増しながら腰をゆすった。
あまりにきつく抱きしめられて、骨がきしむようになりながら、二人のリズムが荒々しく高まっていく。
サムが「くそ、ウエスト」と絞り出し、マグマのように熱いほとばしりを噴出させた。
ジェイソンの絶頂は、背骨の付け根から膨れ上がってくるような一瞬後、はじけとんだ。
終わっても、どちらも動かなかった。体を重ねてまどろみながら、ただ夜空をゆるやかに渡る星々や、流れる銀の雲を眺めていた。
次にジェイソンが目覚めたのは、携帯電話の耳ざわりなうなりのせいだった。
何とか現実世界へ意識を戻し、ゴソゴソと携帯をまさぐっていると、右隣でサムも同じことをしているのに気付く。
「俺のだ」と肩ごしにサムが言ったので、ほっとして顔から枕に崩れた。目をとじて意識を手放そうとするが、いくら粘っても眠りの中に戻れもしないし、サムの側の会話がどうしても耳に入ってくる。
「いいや。続けろ」
沈黙。
いやそうではない、電話の向こう側の誰かの声が小さくザザッと聞こえてくる。火が出る前の電気のショートのように。
サムが小さく毒づき、マットレスを沈ませて立ち上がると、窓に向かった。ジェイソンは頭を上げる。大きな窓の前に立つサムのシルエットが見えた。耳に携帯を当てて、サムはジェファーソン記念館を見下ろしているようだった。ジェイソンに気を使って声を抑えているが、そのせいで向こう側からザアッと届く小さな女の声が、かえって聞き取りやすくなっている。ジョニーだろう。行動分析課【BAU】に加わって間もないが、ジョニー・グールドはあっという間にこの上司にとって欠かせない存在になってのけた。
大したものだ。サムが仕事上で“欠かせない”人間など、ジェイソンにはほかに心当たりすらない。
「わかった。ナショナル空港からの一番早い便に俺の席を取ってくれ」
電話向こうのちっぽけな声が抗議を始める。
サムがさえぎった。
「お前は副部長に報告してこい。いい経験だ」
抗議の声が大きくなる。サムはにべもなく「決定事項だ」と言って切った。
ジェイソンは無音で口笛を吹く。
サムがベッドに戻った。その重みでマットレスが沈む。互いの腕の中に戻ると、ジェイソンは呟いた。
「ジョニーが辞めたら、あなたの自業自得ですよ」
「彼女は辞めない。この仕事が生き甲斐だからな」
たしかに。いや、それは違う。サムの部下の誰ひとり、サムほどこの仕事が生き甲斐の者はいない。
ジェイソンは頭を傾け、薄闇の中でサムの横顔を見つめた。
「どこに向かうんです?」
「アイダホだ」
アイダホは、いつものサムの移動ルートにはない。ジェイソンは考えをめぐらせた。
「カウボーイ・アイクですね」とサムが管理職に昇進する寸前の、現場捜査官として最後の仕事の一つを名指しする。「あの事件が何か?」
「市長と州検察で内輪もめの権力争いだ」
「は? どうして――」
「証人が証言撤回した」
「げ」
「警察の基本的捜査能力の著しい低下だな」
おっと、その演説は前にも聞いた。
「今から現地に行って何かできるんですか?」
「行けばわかる」とサムはむっつり言った。苛ついた息を長くこぼして、上の空でジェイソンの髪をなでる。「まあいい、起きる時間までまだ二時間ある」
ジェイソンはうなずき、目をとじた。数秒、二人の呼吸の静かなリズムが重なる。
この四日間を共にすごし、週末の大部分は眠っていたものの、運河沿いの小さなあの家で、サムの存在は心強かった。再会は何週間も先だろうと思うと、ほとんど身を切られるように痛い。胸がつぶれそうで、息が深く吸えない。
今さらだ、前と何も変わっていないのに。変わったことといえば、この一週間の出来事でジェイソンが理解したことだけだ――別離はサムにとってもつらいことなのだと。
ジェイソンは呟いた。
「さよならを言うのが、段々つらくなってきた」
「ああ」とサムが答えた。
--続きは本編で--